本年度のビジネス書大賞を受賞した『ゼロトゥワン』を何故あらゆるビジネスマンが読むべきか
本年度のビジネス書大賞受賞作は、シリコンバレーの起業家、ピーター・ティールによる著作『ゼロトゥワン』だった。
私はこの本を読むべき理由について語る資格がある、と思っている。
それは恐らく現在の日本において、私はこの本を最も深く読み込んでいる人間のトップ10に入ると思うからだ。

私は現時点で、日本語版の紙書籍と、原書版の紙書籍に加え、Kindleで購入した日本語版電子書籍と、果てには総収録時間4時間強にわたるオーディオブックも持っている。(ちなみに彼の伝記が掲載された『綻びゆくアメリカ』も読んだし、本の出典となったCS183のノートもいくらか読んだ。)
そして、それら全ての媒体を通して、この本の内容に触れた。
できる限りのところまで深く踏み込むように努めた。
ちなみにティールが日本で講演をしたときも会場で参加していた。
そして、明日はビジネス書大賞受賞記念講演会に聴衆として参加するつもりでいる。
翻訳書なのだから原書を読めば一層の理解が深まるのは当然のことだが、Kindleで全文検索しながら読むことで全体の構造を大づかみし、オーディオブックの抑揚ある音声で聞くことで、各文章のどこに重点があるのかも把握した。
そんな読み方だったから、金はやたらかかった。時間もかかった。
しかし、この本にはそれだけの価値があった。
以下では、著者、日本語版序文著者、翻訳者、編集者のそれぞれの観点から、この本がなぜ読む価値のある本なのかを述べていく。
( なおこの記事は、友人への推薦目的で書いている。)
著者について
著者ピーター・ティールは、失敗者である。
この点を読み逃すと、彼の主張が正しく捉えられない。
ティールが失敗者であるとは、一見するとおかしな話だ。
Zero to Oneは、ペイパルというネット決済の大企業を創設し、株式によって5,500万ドルという巨額の個人資産を築いたビジネスマンの話ではなかったのか?
ティールの一般的な経歴が説明される際も、東京駅マルゼンで見たZero to Oneの書店員ポップの説明でも、彼が失敗者であることは触れられていない。
ロースクールの学生の世界で何を一等賞と見なすかは定かでないけれど、何万人という卒業生の中で最高裁の法務事務官になれるのは数十人だ。僕は連邦控訴裁判所の法務事務官を一年務めたあと、ケネディ判事とスカリア判事の事務官の面接に呼ばれた。どちらの面接もうまくいった。最後の競争に勝つまであとすこしだった。もし最高裁の法務事務官になれたら、人生安泰だと思っていた。でも、僕はなれなかった。その時は死ぬほど落ち込んだ。(Zero to One 第4章『イデオロギーとしての競争』より引用)
そして、Zero to Oneだと本人も触れていないのだが、彼はそのあとの転職も立て続けに失敗しているのである。
…(連邦最高裁判所の判事アントニン・スカリアとアンソニー・ケネディの面接を受けたが不採用となったーー彼にとっては人生初の挫折であり、大きな心の傷となった)。その後ニューヨークの一流法律事務所サリヴァン&クロムウェルに採用され、証券取引法を担当した。…(中略)…
仕事は退屈だった。彼がマルクス主義者なら、「阻害された労働」と表現したことだろう...(中略)...
法律事務所は7ヶ月で辞め、クレディ・スイスでデリバティブ(通貨オプション)のトレーダーとして働き始めた。…(中略)...ウォール街でもサリヴァン&クロムウェルと同じ問題に直面した…(中略)...ティールは社会構造によって定義される立場に意義を見いだせないまま、同僚と無我夢中で張り合っていた…(中略)...ゲームを極めて勝利をつかむことができるか不安もあった。彼は人をおだてたり、裏切ったりという政治的駆け引きができるタイプではなかった。
(『綻びゆくアメリカ』 「ピーター・ティール 1」の節より引用 )
就きたかった職業の面接で落とされ、
転職先では自分の希望に合わない業務に付かされる。
仕事には意義が見いだせず、打ち込めない。
そして上司からの評価は、自分が苦手な能力を基準として、不本意に付けられる…。
そのときの彼はきっと、日本で「ただの東大卒」と揶揄される人たちと何ら変わりがなかっただろう。
十数年に渡って築き上げてきた大変なハイスペックを、
何も活かしきれていない。
教育投資の明らかな失敗。
だが、この経験は、彼を最終的に一つの確信に向かわせることになった。
それは、競争は資本主義の対義語である、という逆説的な確信である。
類義語(Synonym)ではない。対義語(Antonym)である。
そして彼はこの確信を証明するかのように、
ペイパルで「隠れた」独占を築くことで、成功者になった。
この確信を持っていたからそういう勝ち方をしたのか、
それともそういう勝ち方をしたからこのような確信に至ったのか。
鶏卵問題の順序は定かではない。
だが、肝心なのはその順序ではない。
巨大決済企業ペイパルの創業は、もう二度と起きない。
ビジネスに同じ瞬間は二度とない。次のビル・ゲイツがオペレーティング・システムを開発することはない。次のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが検索エンジンを作ることもないはずだ。次のマーク・ザッカーバーグがソーシャル・ネットワークを築くこともないだろう。彼らをコピーしているようなら、君は彼らから何も学んでいないことになる。(Zero to One 「はじめに」より引用)
我々にとって最重要なのは、彼が主張するその「競争は資本主義の対義語である」という第一原理、すなわち「独占を計画的に築く」というビジネス戦略を、自分の文脈で考えてみることだ。
ゼロトゥワンという書籍は、そのための叩き台を提供してくれる。
ビジネス書大賞としてZero to Oneがふさわしい理由は、
この極めて直観に反する思想を、非常に納得度の高い事例の数々とレトリックのもとに、書籍の形に結集していることにある。
この極めて直観に反する思想を、非常に納得度の高い事例の数々とレトリックのもとに、書籍の形に結集していることにある。
そして私は、この思想は、心に何かの失敗の経験を抱えている我々のような凡人にこそ、現状突破の鍵になる戦略だと思っている。
利益とは何なのか。競争とは何なのか。失敗とは何なのか。グローバリゼーションによるコモディティ化が加速しているいまこそ、失敗者ピーター・ティールの成功戦略を通して自分で考える価値がある。
(なぜ「自分で」に線を引いたのかは、同書を読んでもらえれば分かる。)
ところで
Zero to Oneは日米同時発売の翻訳書である。
そして翻訳書に付きまとうのが、
「日本語版と原書の英語版、どっちを読んだら良いのか?」
という悩みである。
結論を言うと、日本語版を読むべきである。
日本語版ゼロトゥワンは、後述する序文著者・翻訳者・編集者という3者のはたらきによって、初心者からすると、英語版ゼロトゥワンより遥かに内容が理解しやすい書籍になっている。
私は英検1級保持者だが、原書は単語が難しいため理解しづらい。とくに、人名やアダ名(たとえば「八人の反逆者」Traitrous Eightなど)はそもそも単語力の勝負ですらない。Jack Dorseyや、Sheryl Sandbarg、Marissa Mayerなどの人名を見て、どの会社で何やった人かがピンと来ないと、事実関係がうまく掴めない。原書の一周目は、基本的に日本語版と首っ引きで読んでいた。
序文著者の功績
日本語版序文は、エンジェル投資家の瀧本哲史氏が書いている。彼は、ティールと多くの属性を共有している。
2人とも飛び級経験者で、思想的にはリバタリアニズムであり、「目の前にあるのに見えないという意味で隠れた真実」の価値を重視する。おまけに法学部出身であり、フランシス・ベーコンの思想に言及している点でも共通している。
Amazonを見るとこの序文は「読みづらい」だのと低評価なのだが、この序文も実は上のような共通性を知った上で見ると、本書を理解する上でむしろ大きな手助けとなる。ひとつ、例を挙げてみよう。
ただ一方で、ウェブで読めるような「◯◯を成功させるための10の法則」的な、内容を薄めた本じゃないのかと、心配にもなるだろう。安心して欲しい。実は、ティールはそんな単純な人物ではないし、本書もそんな「わかりやすい」本ではない。(日本語版序文より引用)
繰り返すように、彼はティールと極めて多くの属性を共有しているにもかかわらず、ティールが書いたこの本を「わかりやすくない」と言っているのである。
それに加えて、瀧本氏の講演会に行ったことがある人なら同意してくれるだろうが、氏の瞬間的な理解力はすさまじい。質疑応答セッションで、どう考えても質問になってないだろそれみたいな問いが出た場合でも、瀧本氏は即座に質問者の意図を見抜き、それに呼応する答えを返す。僕のような一般聴衆は「あれ、さっきの質問、案外ちゃんとしてたんだな」と思い込まされるので、質問者も聴衆も誰もその質問がヤバかったと気づかないまま話が進んでいく。
だいたいその場にいる誰よりも早く複雑な内容を理解してきた、その瀧本氏が、本書は「わかりやすくない」と言っているのである。
これは、本書を読む上で非常に重要なヒントである。
これは、ゼロトゥワンが、気を抜くと簡単に字面を追えてしまうからである。
例えば第二章「1999年のお祭り騒ぎ」では、「1990年代にはいいイメージがある」という一文から、歴史的事件の羅列のような文章が続く。ベルリンの壁の崩壊、ソマリアのアメリカ兵、メキシコへの雇用流出、半導体戦争、アジア通貨危機、そして1998年からのドットコムバブル。この殴るような列挙が実はレトリックであるということを認識しないと、この章は感想が残らない。
この章は、
1.なぜ1990年代後半のバブルに皆があれだけ期待したのか
2.スタートアップという観点から見ると、なぜバブルは崩れたのか
3.バブルから私たちが学んだと思い込んでいる教訓が、本当に正しいのか
という、バブルにまつわる認知のゆがみを、以上のようなレトリックによって説明しようとしている。特に私が驚愕したのは3.で要するにティールはバブルのときに生じていた「雰囲気」に少しばかり賛成しているのだ。教訓が間違いで、バブルのときの「熱気」のほうが正しいということを、この章では示唆し、そして10章「マフィアの力学」では、「コンサルタント」と「カルト」という言葉で関連話題について更に深く追っている。
翻訳者の功績
翻訳者は杏里大学准教授の関 美和氏という方で、これまでにも相当な数の翻訳書を手がけてきたベテラン翻訳者のようだ。
Zero to Oneの翻訳は、非常に読みやすい。
それには理由がある。
翻訳者が、著者の主張を正しく理解しているのだ。
上では述べなかったのだが、私は偶然にもZero to Oneの「未校正版」というレア本を持っている。知人の家を訪れたら、たまたま本棚にあったので借りたのだ。
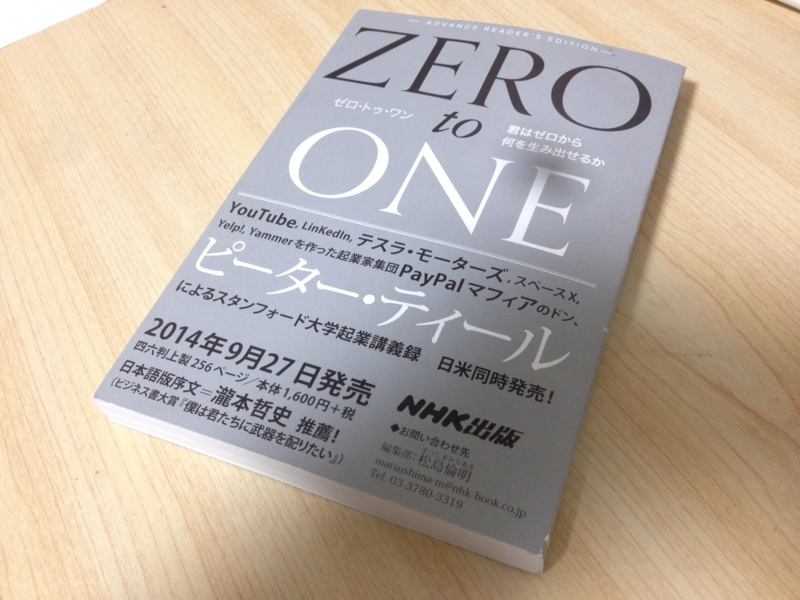
( これが未校正版だよ↑ )
読み始めて驚愕した。
未校正版では、翻訳がかなり違うのである。
そして出版されたバージョンのほうが、遥かにわかりやすい。
最も顕著な例を挙げる。
Zero to Oneの第5章は、原書ではLast Mover Advantageという章題が付けられている。これはFirst Mover Advantage(先発者利益)を追うよりも、タイミングに関しては他の戦略で打って出たほうが良いということを表している。
だが、このLast Mover Advantageという表現は、実に誤解を招きやすい。どこで見かけたか忘れてしまったが、英語圏のウェブサイトで「Lastに動いてどうして勝てるんだ?」という感想を見かけた記憶がある。そして実際にティールがこの章で主張したいことは、必ずしも字面通りの「ラスト」ではないのだ。
ティールはこの例に限らず、二項対立を説明する際に「最も極端なもの」を表す単語を用いるクセがある。たとえば第3章で説明される「完全競争(Perfect Competition)と独占(Monopoly)」の話では、実際に例に出てくるのはどれも不完全競争と寡占だったりする。だから、原書で読む時には常に頭の中で概念の変換をかけていく必要がある。
では、日本語未校正版の原稿では章題はどうなっているのかというと、
後発優位 (ルビに「ラストムーバー・アドバンテージ」)
となっている。うん、わかりやすいようで、いまいち掴めない。
そして出版されたバージョンでは、
終盤を制する(ルビに「ラストムーバー・アドバンテージ」)
となっている。これは、章の最後で引用されるチェスのグランド・マスターの警句を踏まえた意訳だろう。ビジネスにおいて、独占利益を享受するための施策は、終盤を制せるかどうかにある、という章の大筋を踏まえたタイトルになっている。
そしてこの翻訳の質の高さを理解するために、何よりも注目すべきは、Zero to Oneは日米同時発売だということである。
つまり、翻訳者は僕のように、英語版書籍の読者の「ラストムーバーってなんだ?」という疑問を観測してから翻訳を改訂した訳ではない。
あくまでも、Last Mover Advantageという章題の付いた章では「ゲームに勝ちたいのなら、何よりもまず終盤を制することだ」ということが述べられているから、そう訳したほうがよいと判断したということだろう。
このような、読者のことを考えた翻訳で溢れているから、
日本語版書籍は原書より遥かに読みやすい。
僕のように、翻訳に興味がある人間にとっても、お手本的な訳がたくさん載っている。
編集者の功績
日本語版Zero to Oneがもう一つ決定的に読みやすい理由は、注釈の位置である。
ページの下に注釈があるため、章末に注釈がまとまっている従来型の傍注と違い、パッと分からない用語を調べることができる。注釈の数は非常に多く、読解の大きな手助けとなる。これは編集者・松島倫明氏の功績だろう。
ちなみに本全体のデザインも、(原書にない)オレンジ色の透かしが入っていたり、フォントが読みやすかったり、図の位置が分かりやすかったりと、非常に好感がもてる。
おわりに
私は普段、そんなに本を読むタイプではない。ましてや同じ本を繰り返し読むなんて、人生で片手ぐらいしか行ったことがない。
そんな私がここまで打ち込んで読めたのは、とにかくZero to Oneがそれだけの、何度も読むに耐える内容を秘めた本だからだと思う。
外国の掲示板サイトRedditでは、ティールが本は相当構成して詰め込んだという発言を投稿している。そもそも、本のもとになった授業から出版まで2年以上の月日がある。きっと相当練り込んで執筆したのではないかと推察される。
厚さにしてわずか200ページ強の書籍だが、 その記述の統制度合いは恐ろしいものがある。僕は読んでいて、哲学書とはこういうものかという感慨を抱いた(ティールはもともと、学部時代は哲学を專攻していた)。
そして前述のように、日本語版作成に関わったどのスタッフも、本を読んだ限りはそれぞれの職務を効果的に果たしている。
あらゆるビジネスマン(含む、社会人1年目の友人)に、僕はこの本を薦めたいと思う。
ちなみに原書もオススメです(僕は蔦屋書店で買いました)

Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future
- 作者: Peter Thiel,Blake Masters
- 出版社/メーカー: Crown Business
- 発売日: 2014/09/16
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る

